はじめに
注文住宅の最大の魅力のひとつが「間取りの自由設計」です。
でもその分、「間取りで後悔した…」「実際に住んでみたら使いづらかった」という声も後を絶ちません。
実は、家づくりで最も後悔が多いポイントは、水回りの動線と収納不足だと言われています。
間取りの打ち合わせは、最初の段階でどれだけシミュレーションできるかがカギ。
この記事では、実際に家づくりを経験した目線で、打ち合わせ時に気をつけるべき5つのコツをお伝えします。
これを知っておけば、完成後に「こうすればよかった…」と後悔するリスクを減らすことができます。
コツ① 生活動線を徹底的にシミュレーションする
まず最優先にすべきなのが生活動線の確認です。
よくある失敗は、「間取り図上ではスッキリしていたけど、暮らしてみたら遠回りだった」というケース。
✔ よくある生活動線のチェック例
- 帰宅後 → 玄関 → 手洗い → 着替え → リビングまでの流れ
- 洗濯 → 干す → たたむ → 収納の動線が一筆書きになっているか
- 買い物後、キッチンまで荷物がすぐ運べるか(勝手口・パントリー)
特に子育て世代なら「ただいま動線」「洗濯動線」「お風呂・トイレの動線」などは暮らしやすさに直結します。
家族全員の1日を紙に書き出してみると、必要な動線が見えてきます。
コツ② 収納率15%を目安に“収納計画”を立てる
「収納は多めにとっておけば大丈夫」…と思っていませんか?
実は、収納にもバランスと配置がとても大切です。
おすすめは、床面積に対して15%前後の収納スペースを目安に確保すること。
たとえば33坪の家なら約5坪(≒10畳弱)が理想です。
✔ 必要な収納の具体例
- シューズクローク(アウトドア・釣具・ベビーカー)
- パントリー(買い置き食材・キッチン用品)
- ランドリー周辺(下着・タオル・洗剤)
- ファミリークローゼット(洗濯動線と連動)
収納の量だけでなく「使う場所の近くにあるか」も重要です。
収納は「動線の途中に仕込む」とグッと暮らしやすくなります。
コツ③ 廊下はなるべく“無駄なく”使う
注文住宅では、「できるだけ廊下を減らして居室を広くしたい」と考える方が多いです。
でも、廊下がないと動線が交差して使いづらくなることも。
特に気をつけたいのが、玄関ホール・洗面所・LDKへのアクセスがごちゃつくケース。
来客時の視線やプライバシーの面でも、廊下でゆるく空間を区切るのは有効です。
実際に我が家でも、ランドリールームとファミクロに繋がる1畳程度の“つなぎ”スペースがかなり便利。
「廊下=無駄」ではなく、「回遊性を生む最小限の余白」として考えるのがポイントです。
コツ④ 家具・家電のサイズを先に決めておく
意外と多いのが、「ソファが通らない」「冷蔵庫の扉が開ききらない」といったサイズ問題。
間取りの打ち合わせ前に、将来置く予定の家具・家電サイズをメモしておくのがおすすめです。
✔ 要チェックのポイント
- ドラム式洗濯機の設置スペースと開閉方向
- ダイニングテーブルと椅子の引き幅
- 冷蔵庫+背面収納の距離(通れるか)
- ソファとテレビの距離
とくにドラム式洗濯機の配置ミスは致命的になりがちです。
横幅・奥行・扉の開閉まで含めたサイズでシミュレーションしましょう。
コツ⑤ 迷ったら“後から変えられない部分”を優先する
間取りの打ち合わせでは、あれもこれもと迷うのが当たり前です。
そんなときの判断基準は、「後から変えられないものを優先する」こと。
たとえば以下のようなものは、あとでリフォームするにはかなりコストがかかります。
✔ 後から変えにくいもの
- 建物の方角と採光(特にLDK)
- 階段の位置
- 水回りの配置(お風呂・トイレ・洗面)
- 吹き抜け・勾配天井・天井高
逆に、棚や照明、家具などはあとからでも対応できます。
限られた打ち合わせ回数の中では、「今しか決められない部分」に集中することが大切です。
まとめ|「暮らしの視点」で間取りを考えよう
間取りの打ち合わせで失敗しないためには、図面を眺めるだけでなく、“暮らす視点”で想像することが大切です。
設計士さん任せではなく、家族の動き・使い方・ストレスになりそうなことを一つずつ洗い出していく。
少し手間はかかりますが、それが「住んでよかった!」につながる一歩
✔ 今回の5つのコツを振り返り
- 生活動線をとことんシミュレーション
- 収納は“量と配置”が重要
- 廊下は「余白」として活用
- 家具・家電のサイズは先に決めておく
- 迷ったら“後から変えられない部分”を優先
間取りづくりは「図面の中で暮らす」練習。
後悔しない家づくりのために、じっくり丁寧に向き合っていきましょう!




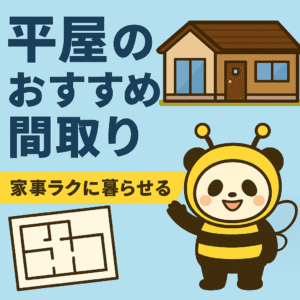




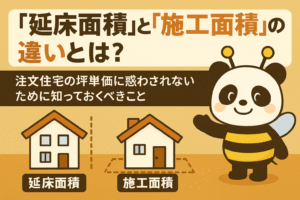
コメント