「注文住宅って、高いよねぇ〜」
これは、家づくりを始めたばかりのころ、我が家でも何度も出てきたセリフです。
住宅ローン、土地代、建築費、外構費、そして家具や家電の買い替え……気づけば軽く数千万円。
でも、ちょっと待ってください。
そんな大きな出費のなかでも、「実はもらえるお金」があることをご存知でしょうか?
住宅購入における「補助金」「助成金」は、国・自治体・工務店など複数の主体から提供されており、うまく活用すれば数十万円〜100万円以上の支援を受けられることも。
しかも、多くの人が「知らなかった」「気づいたときには申請期限を過ぎていた」と後悔しているのが現状です。
このページでは、住宅購入・家づくりを考えているすべての方に向けて、
2025年最新の補助制度を、FP目線でわかりやすく整理してご紹介します。
特に、今年から始まった「GX指向型住宅支援制度」や、定番の「住宅ローン控除」「ZEH支援事業」など、最新トピックも交えています。
これから建てる人はもちろん、契約後でも間に合う制度もあるので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
1. 注文住宅で使える補助金・助成金の全体像
「補助金って、どうせ一部の人しかもらえないんでしょ?」
家づくりを始める前、そう思っていた方も多いかもしれません。
でも実際には、収入や家族構成、建てる家の性能などに応じて、想像以上に多くの人が対象になる制度がそろっています。
大きく分けると、住宅関連の補助金制度は次の3種類に分類されます。
- ① 国の制度(例:住宅ローン控除、ZEH補助金、GX支援など)
- ② 自治体の制度(例:若者・子育て世帯向け、移住支援など)
- ③ 地域連携・ハウスメーカー経由の制度(例:地域型住宅グリーン化事業など)
たとえば、太陽光発電+高断熱住宅を建てれば「ZEH補助金」が活用できますし、自治体によっては子育て世帯向けに「住宅取得補助」や「引っ越し費用の助成」があるところも。
ただし、注意点もあります。
それは多くの制度が「契約前」または「着工前」でないと申請できない点。
あとから気づいても間に合わないケースがあるため、情報収集は家づくりの初期段階が超重要です。
また、補助金の内容は毎年アップデートされるため、「去年はあった制度が今年はない」「新しく始まった制度に該当するかも」といったことも。
このあと、各制度の具体的な内容や注意点を詳しく解説していきますので、
「自分がどの制度を使えるか?」という視点で読み進めてみてください。
2. 国の制度|2025年に使える住宅関連の支援一覧
まずは、全国どこに住んでいても対象となる「国の制度」から見ていきましょう。
2025年現在、特に注目すべき支援制度は以下の通りです。
- 住宅ローン控除(13年間)
- ZEH支援事業
- 地域型住宅グリーン化事業
- GX指向型住宅支援制度(新設)
■ 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを組んで新築・購入した場合、年末ローン残高の0.7%を最大13年間にわたり所得税や住民税から控除できる制度です。
特に、省エネ基準を満たした住宅では、控除対象額の上限が引き上げられる点もポイント。
ただし、以下のような条件に注意しましょう。
- 合計所得金額が2,000万円以下
- 住宅の床面積が50㎡以上(所得が1,000万円以下なら40㎡以上でも可)
- 登記簿上の所有者がローンの借入者であること
■ ZEH支援事業
「ZEH(ゼッチ)」とは、断熱性や省エネ性を高め、太陽光発電などでエネルギーを自給自足できる住宅のこと。
対象となる住宅を建てると、以下のような補助金が受け取れます。
- ZEH:55万円
- ZEH+:90万円
- ZEH Oriented(太陽光なし):条件により一部補助
我が家でもこの制度を申請済みで、交付決定通知を受け取った段階です。
着工前に工務店と連携しながら申請準備を進める必要があるので、早めの相談がカギになります。
■ 地域型住宅グリーン化事業
地域の中小工務店による木造住宅を対象に、省エネ・耐久性に優れた住宅を建てた場合に補助される制度です。
こちらは事業者(工務店)側の申請が前提なので、自分が使えるかどうかは契約予定の施工業者に確認しましょう。
■ GX指向型住宅支援制度(2025年新設)
旧「こどもエコすまい支援事業」の後継として登場した新しい制度です。
高断熱性能+高効率設備を備えた住宅を対象に、最大160万円の補助が出る可能性があります。
詳細条件については記事を分けて解説していますので、こちらをご覧ください👇
このように、国の制度だけでも数十万円〜100万円超の支援を受けられる可能性があります。
次は、場所によって内容が大きく変わる「自治体の制度」について解説します。
3. 自治体の制度|住宅購入に使える実在の補助金例
国の制度とは別に、見逃せないのが「市区町村の支援制度」です。
特に、若年層・子育て世帯・移住者向けに手厚い支援を行っている自治体が増えています。
ただし、ここで注意が必要なのは地域によって内容も金額もまったく違うということ。
「東京23区にはないけど、地方都市にはある」
「同じ県内でも市によって制度が全然違う」
こんなことも珍しくありません。
■ 実例:2025年4月時点の自治体支援
以下は、2025年4月時点で実際に確認できた支援制度の一例です。
- 東京都:東京ゼロエミ住宅助成事業
高い省エネ性能を持つ新築住宅を対象に、性能水準に応じて最大240万円の補助金が支給されます。
さらに、太陽光発電設備の設置には最大39万円、蓄電池には最大95万円の補助もあります。 - 神奈川県秦野市:はだの丹沢ライフ応援事業
40歳以下の世帯が市内に新築住宅を取得する際に、基本額20万円に加え、条件に応じて最大60万円の加算が受けられます。 - 北海道新十津川町:新築・中古住宅取得助成事業
新築住宅を購入した方を対象に、町内業者施工で最大230万円、町外業者施工で最大190万円の助成金が支給されます。
このように、金銭支援の形式も「住宅取得費の補助」「再エネ設備設置の補助」などさまざまです。
■ どうやって調べる?
補助金の有無は、「自治体名+住宅 補助金」「移住支援金」などで検索するのが一番確実です。
また、地域によっては住宅会社や不動産会社が情報を取りまとめてくれていることもあるので、見学や相談のタイミングで聞いておくのもおすすめです。
■ 申請タイミングと注意点
自治体の制度は、年度ごとの予算で運営されているため、以下のような注意点があります。
- 受付が「予算上限に達し次第終了」となることが多い
- 申請期限が早めに設定されていることもある(例:3月中旬締切)
- 引越し後に申請不可のパターンもある
つまり、「建てる場所を決めたら、すぐに補助制度を調べる」のが鉄則です。
続いては、実際に我が家がどういった制度を使えたか、また使えなかったかについて、体験ベースでご紹介します。
4. 我が家が使えた制度・使えなかった制度【体験ベース】
住宅に関する補助金や助成金って、仕組みが複雑だし、どこまで本当に使えるのか疑問に感じる人も多いはず。
そこで参考までに、我が家のリアルな活用状況をご紹介します。
■ 使えた制度:住宅ローン控除(ペアローン)
我が家は夫婦の収入バランスを考慮してペアローンを選びました。
これにより、それぞれで「住宅ローン控除(13年間)」を受けられる形に。
結果として、1年あたりの控除額は2人合計で約20〜30万円。
13年間継続されることを考えると、控除総額で300万円超の恩恵が見込めます。
ポイントは「夫婦どちらも収入がある場合は、ローンも分けて考えると控除も2倍になる可能性がある」という点。
このあたりは所得バランスと相談しながら戦略的に組むのがおすすめです。
■ 申請済み:ZEH+支援事業(90万円)
我が家では、太陽光発電と高断熱性能に加えて、高効率設備も備えたZEH+仕様の住宅を建てました。
そのため、ZEHの中でも上位グレードにあたる「ZEH+」の補助金対象(90万円)となり、申請も完了済み。交付決定通知も受け取っています(※振込はまだ)。
この補助は、断熱性だけでなく、給湯や換気などの設備の効率も基準を満たす必要があり、仕様決めの段階から制度を意識することが重要でした。
■ 使えなかった制度:こどもエコすまい支援事業
検討中に存在していた「こどもエコすまい支援事業」は、すでに予算終了となっており対象外に。
結果的に、「GX指向型住宅支援制度」の活用を視野に入れる形にシフトしました。
このように、「知っていたけどタイミングが合わず使えなかった」というケースもあるため、補助金情報の早期収集が本当に大切です。
■ 補助金は“情報戦”
住宅関連の補助金は、申請タイミングや条件が厳しい一方で、使えたときのインパクトは絶大。
特にZEH+やローン控除のように、数十万〜100万円規模の補助が出る制度は「家計全体のバランスを左右する」レベルです。
次は、補助金制度の「落とし穴」と、活用時に気をつけたいポイントについてまとめていきます。
5. 知らないと損する?補助金活用の注意点とまとめ
ここまでで、住宅購入時に使える補助金や助成金について、国の制度から自治体制度、我が家の実例まで紹介してきました。
でも、最後に忘れてはいけないのが「注意点」。
せっかくの制度を“うっかり”で逃してしまうケース、実はとても多いんです。
■ よくある落とし穴 3選
- 着工後では申請できない制度が多い
特に国の補助制度は「着工前」が申請の基本ルール。
工事が始まってから「補助金あるって聞いたけど…」では手遅れになることも。 - ハウスメーカーが対応していないケースもある
補助金の申請は事業者(工務店やハウスメーカー)側が代行するものもあり、対応していない会社もあります。
契約前に「この制度、対応してますか?」と聞いておくのが◎。 - 制度は毎年変わる
昨年はあったのに今年はない、逆に今年から新しく始まった制度がある、など補助金は“生き物”です。
最新情報のチェックは必須。自治体サイトや公式広報を見ておきましょう。
■ 家づくりは“制度との戦い”でもある
「予算はギリギリだけど、補助金で何とかなるかも」
「性能を上げれば補助金の対象になる」
「手続きは面倒だけど、やる価値はある」
補助金は、“少し先の将来の安心”を買うための第一歩でもあります。
そしてそのチャンスは、「知らなかった」で逃してしまうのは本当にもったいない。
■ まとめ:制度を知れば、家づくりはもっと賢くなる
- 補助金・助成金には国・自治体・工務店連携の3つの軸がある
- 条件・時期・性能要件などを満たせば100万円以上の支援も可能
- 情報収集とタイミングが成功のカギ!
最後に、ペアローンやZEH、GX制度についてもっと深掘りしたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
▶ ペアローンって結局どうなの?メリット・デメリットをFPが解説
賢く補助金を使って、少しでもおトクに・安心して、あなたらしい家づくりを進めていきましょう!






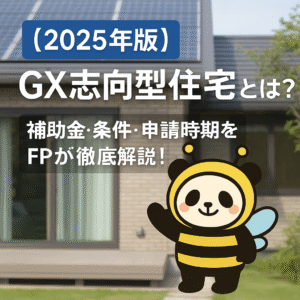


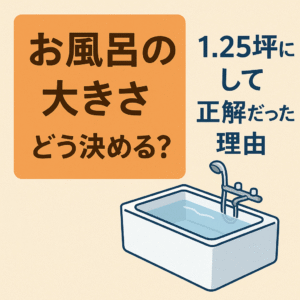
コメント